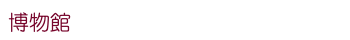萬古焼
萬古焼は、四日市の代表的な伝統産業です。元文年間(1736~1741)に、 この焼き物をはじめたのは桑名の豪商沼波弄山(ぬなみろうざん)でした。 作品に「萬古」の印をつけたことから萬古焼と呼ばれるようになりました。弄山が死ぬと萬古焼はおとろえてしまいますが、天保3年(1832)森有節(もりゆうせつ)が萬古焼を復活させます。 弄山のつくった「古萬古」をまねしただけでなく、 木型による急須(きゅうす)を新しく作りました。 今でも、萬古焼の急須は作り継がれ有名です。 明治時代になると四日市でさかんにおもしろい萬古焼がつくられ外国に輸出されるようになりました。

古萬古四方型大香炉

有節萬古大皿

古萬古銚子

有節萬古急須

明治萬古土瓶
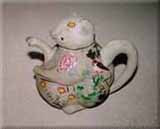
明治萬古急須
四日市祭り
四日市祭りは東海地方の三大祭りに数えられた大きな祭りでした。

大入道(中納屋)

甕割り(商店連合会)

鯨船(富田、南納屋)

けんかまつり(富州原)

お諏訪踊り(水沢)

大念仏(四郷)
昔の道具

火ばち

石うす

こたつ

せいろ

おひつ

せんたく板