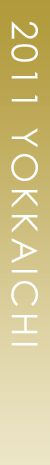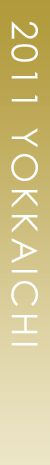| 保険年金課(Tel 354-8161 Fax 359-0288) |
医療保険と介護保険の両方を利用している世帯で、合算した自己負担額が高額になったときに、申請により負担が軽減されます。
両方の自己負担額を年間(平成22年8月〜平成23年7月)で合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合に「高額介護合算療養費」が支給されます。なお、合算できるのは、同じ世帯で、同じ医療保険に加入している人です。 平成23年7月31日現在で国民健康保険か後期高齢者医療に加入の世帯には、該当する場合は市か三重県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内をお送りします。(国民健康保険は市から、後期高齢者医療は広域連合から、いずれも平成24年1月以降に送付の予定です) |
| 合算制度の自己負担限度額(前年8月から7月までの合計、単位:万円) |
保険の種類
医療保険の所得区分
|
後期高齢者医療+介護保険 |
国民健康保険+介護保険 |
| 75歳以上の人 |
70〜74歳の人 |
70歳未満の人 |
| (1)上位所得(注) |
- |
- |
126 |
| (2)現役並み所得(注) |
67 |
67 |
- |
| (3)一般(注) |
56 |
56 |
67 |
| (4)市民税非課税(注) |
II |
31 |
31 |
34 |
| I |
19 |
19 |
|
| (注) |
(1)……… |
基礎控除(33万円)後の総所得額が600万円を超える世帯 |
| |
(2)……… |
医療機関受診時の一部負担金の割合が3割の人 |
| |
(4)のI… |
所得が0円(年金所得は控除額を80万円として計算) |
| |
(4)のII… |
所得があり非課税の場合 |
| |
(3)……… |
(1)・(2)・(4)にあてはまらない場合 |
|
| 自己負担額には、高額療養費や高額介護サービス費として支給された額は含まず、食費や居住費などは合算の対象となりません。 |