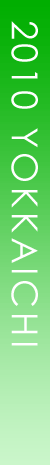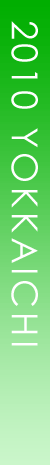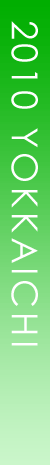 |
|
市外で活躍する四日市出身者からの便りをお届けします。
第1回目は、四日市市を舞台とした映画「いずれの森か青き海」などを制作した、瀬木直貴監督から四日市市へのお便りです。 |
|
|
 |
僕の生家の裏手には小高い丘があります。赤茶けた粘土質の斜面を駆け上がり、ススキやセイタカアワダチソウの茂みを抜けると、丘の頂に到着します。そこから見るまちの様子こそ、私の原風景と言えるものかも知れません。
赤白のストライプの煙突が青空に聳(そび)え、白い息を吐きながら、まちを見下ろしています。無数のパイプやタンクは、斜光を受けて黄金色に染まり、まるで生き物のように有機的に絡み合っています。
石油化学コンビナートは、多くの人に公害の歴史を想起させます。しかし同時に、私は遠望する工場群にある種の懐かしさを感じてきました。もっとも故郷の懐かしさと言っても、山里や水田、お寺や土塀といった風物とは明らかに違うものです。故郷というものが何を意味するのかは、その人の育った環境によって異なるのかも知れません。
私は子どもの頃(ころ)から、流れる煙を見て風の向きを知り、季節を感じてきました。工場の敷地に忍び込んでは魚釣りや昆虫採集に夢中になり、友達と語り明かした朝、赤く染まったプラントを見て、すがすがしい生命力を感じました。
故郷・四日市の原風景。そこには、自然と人工物の、どこかせつなさを漂わせた調和があったように思います。
昨年の帰省の折、久しぶりに丘に上ってこの風景を眺めました。巨大なプラントは廃墟と化し、その向こうには未来都市を思わせる真新しいプラントが、夕陽を浴びてヌメッと光っていました。季節が移り変わるように、風景の調和も絶えず変わっていきます。故郷とはそこから立ち去る場所だという、ヴァージニア・ウルフ(注1)の美しい文章が、ふと脳裏に浮かびました。
(注1)イギリスの女性小説家、評論家(1882〜1941) |
 |
|
|
|
| ●問い合わせ先
…広報広聴課(Tel 354−8244 Fax354−3974) |
|
|
|