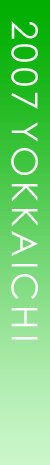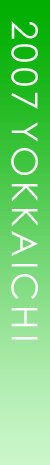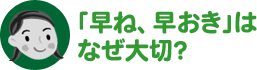 |
|
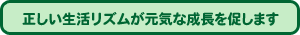 |
|
| ●人間には本来持っている生活リズムがあります |
|
 人間の体は昼には昼動く体の仕組み、夜には夜動く体の仕組みがあり、体温や分泌するホルモンのリズムもそれに基づいて作用するようになっています。そして、そのリズムに合わせて生活したときに最も能力を発揮できるようになっています。 人間の体は昼には昼動く体の仕組み、夜には夜動く体の仕組みがあり、体温や分泌するホルモンのリズムもそれに基づいて作用するようになっています。そして、そのリズムに合わせて生活したときに最も能力を発揮できるようになっています。 |
|
| ●早おきで1日の生活リズムがスタート |
|
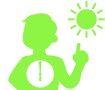 人間の脳の中には体内時計をつかさどる機能があり、この時計に基づいて睡眠、体温、ホルモン分泌のリズムを刻んでいます。この機能で朝の光をキャッチすると、体内時計が始まり、1日の正しい生活リズムが刻まれます。早おきして朝の光をいっぱい浴びることが元気な1日のスタートになります。 人間の脳の中には体内時計をつかさどる機能があり、この時計に基づいて睡眠、体温、ホルモン分泌のリズムを刻んでいます。この機能で朝の光をキャッチすると、体内時計が始まり、1日の正しい生活リズムが刻まれます。早おきして朝の光をいっぱい浴びることが元気な1日のスタートになります。 |
|
| ●就寝中に分泌される成長ホルモン |
|
夜、寝入りばなの深い睡眠の時に成長ホルモンが多く分泌されます。成長ホルモンは、新陳代謝を活発にして脳やからだの成長に深く関わるものです。
また、子どもの成長に大切な役割を果たすと考えられているメラトニンというホルモンは、夜になると分泌され、鎮静作用のほか、細胞を酸化から守り、老化防止や抗癌(がん)作用、また第二次成長を抑える作用があるといわれています。メラトニンは、1〜5歳のころに分泌のピークを迎え、また、目が光を感じていると分泌が抑えられ、感じないと分泌が始まります。
|
|
[グラフ(1)]睡眠とホルモン分泌の関係
資料/「子どもの睡眠」神山潤著(芽ばえ社)より |
|
![[グラフ(1)]睡眠とホルモン分泌の関係](img/sp_02/graf01.gif) |
|
 |
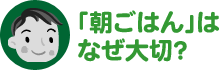 |
|
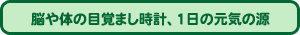 |
|
| ●脳や体の活性化に欠かせない栄養分 |
|
| 朝ごはんをとると脳のエネルギーの基となるブドウ糖を取り入れることができます。体を動かすエネルギーの補給にもなります。また、寝ているときに下がった体温を上げることもできます。朝ごはんは脳や体の目覚まし時計です。 |
|
| ●朝ごはんを食べないと、疲れやすく集中力も不足 |
|
| 朝ごはんを毎日食べる人と食べない人では疲労感や集中力に差が生まれます(グラフ(2)(3))。学校生活を楽しく充実させるためにも、朝ごはんを食べる習慣を身に付けましょう。 |
|
〈市内モデル地域の小・中学校を対象にした「子どもの生活意識調査」から〉
[グラフ(2)]
何もやる気がしなくなる(疲労感)=小学校高学年 |
|
![[グラフ(2)]何もやる気がしなくなる(疲労感)=小学校高学年](img/sp_02/graf02.gif) |
|
[グラフ(3)]
1時間の授業に集中できる(自己効力感)=小学校高学年 |
|
![[グラフ(3)]1時間の授業に集中できる(自己効力感)=小学校中学年](img/sp_02/graf03.gif) |
|
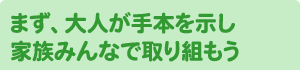 |
子どもたちのための「早ね、早おき、朝ごはん」の市民運動を進めていくためには、各家庭で家族みんなで取り組むことが大切です。
食事中は、テレビを消すなど大人も子どもも生活習慣全体を見直し、みんなで話し合い、正しい生活リズムづくりに努めましょう。 |
|
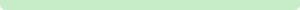 |
|