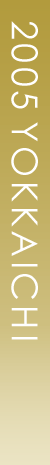 |
|
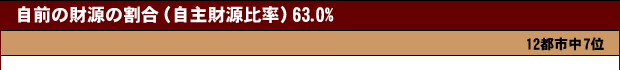 |
財政の自立性の
度合いは平均的

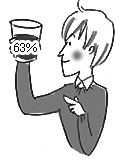 市の収入全体に占める市税、公共施設の使用料や住民票などの発行手数料など、市の自前の財源が占める割合(自主財源比率)は約6割です。この数字が高いほど、国や県からの補助金や交付金などに頼ることなく安定的な財政運営が可能になります。本市の自主財源比率は市税の落ち込みにより、平成12年度以降低下傾向が続いておりましたが、平成16年度は市税収入の増加などにより、前年度より0.6ポイント回復しました(グラフ(1))。 市の収入全体に占める市税、公共施設の使用料や住民票などの発行手数料など、市の自前の財源が占める割合(自主財源比率)は約6割です。この数字が高いほど、国や県からの補助金や交付金などに頼ることなく安定的な財政運営が可能になります。本市の自主財源比率は市税の落ち込みにより、平成12年度以降低下傾向が続いておりましたが、平成16年度は市税収入の増加などにより、前年度より0.6ポイント回復しました(グラフ(1))。 |
 |
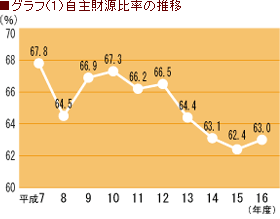 |
|
 |
|
 |
財政力は低下傾向
引き続き交付団体

 財政の豊かさを示す指標に財政力指数があります。国の基準による必要行政経費額に対し、市税などの見込み収入額がどれだけあるかを示す比率で、「1」を超えるほど財源に余裕があり、「1」を下回ると不足分が国から普通交付税として支援されます。本市は平成11年度から「1」を下回り、平成16年度は前年度より0.007ポイント低下し0.910となり(グラフ(2))、依然として交付団体です。 財政の豊かさを示す指標に財政力指数があります。国の基準による必要行政経費額に対し、市税などの見込み収入額がどれだけあるかを示す比率で、「1」を超えるほど財源に余裕があり、「1」を下回ると不足分が国から普通交付税として支援されます。本市は平成11年度から「1」を下回り、平成16年度は前年度より0.007ポイント低下し0.910となり(グラフ(2))、依然として交付団体です。 |
 |
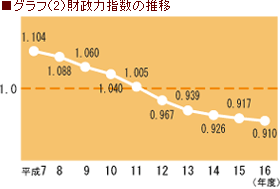 |
|
 |
|
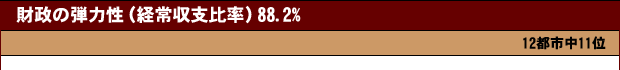 |
財政の硬直化が進み
ゆとりのお金が減少

 財政の弾力性を表す指標に経常収支比率があります。人件費、公債費や福祉に関する経費など経常的に支出する経費が、市税や普通交付税などの一般財源の中に占める割合で、この比率が高いほど新しい仕事に使えるゆとりのお金が少なくなり、財政構造が硬直化していることを示します。本市の平成16年の経常収支比率は88.2%で、前年度より3.2ポイント上昇しました(グラフ(3))。 財政の弾力性を表す指標に経常収支比率があります。人件費、公債費や福祉に関する経費など経常的に支出する経費が、市税や普通交付税などの一般財源の中に占める割合で、この比率が高いほど新しい仕事に使えるゆとりのお金が少なくなり、財政構造が硬直化していることを示します。本市の平成16年の経常収支比率は88.2%で、前年度より3.2ポイント上昇しました(グラフ(3))。 |
 |
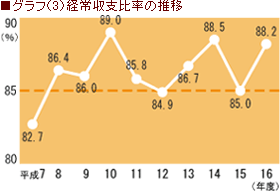 |
|
 |
|
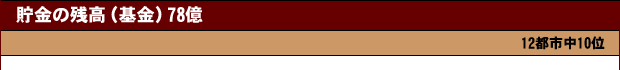 |
財政調整基金の
取り崩しで残高減

 基金は将来に備えた貯金で、財政の過不足を補う財政調整基金や減債基金などがあります。平成16年度決算での基金残高は78億円で、前年度よりわずかに減少しました(グラフ(4))。12都市の平均基金残高は140億円で、本市はその半分程度となっています。そのうち財政調整基金は平成16年度は9億円を取り崩し、残高は21億円となりました。 基金は将来に備えた貯金で、財政の過不足を補う財政調整基金や減債基金などがあります。平成16年度決算での基金残高は78億円で、前年度よりわずかに減少しました(グラフ(4))。12都市の平均基金残高は140億円で、本市はその半分程度となっています。そのうち財政調整基金は平成16年度は9億円を取り崩し、残高は21億円となりました。 |
 |
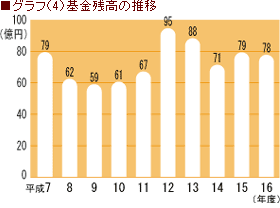 |
|
 |
|
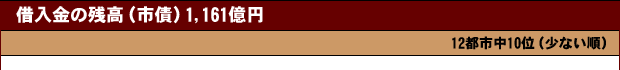 |
発行額を抑制し
実質的な残高は減少

 市債は市の借入金で、単にその年度の資金不足を補うためだけでなく、将来にわたり利用される道路や学校などの整備資金を将来世代にも公平に負担してもらうために行うものです。平成16年度は前年度より27億円増加したものの、旧楠町より33億円引き継いでおり、実質的な残高は減少しました。なお、市債の発行を計画的に行っており、今後は徐々に減少となる見込みです(グラフ(5))。 市債は市の借入金で、単にその年度の資金不足を補うためだけでなく、将来にわたり利用される道路や学校などの整備資金を将来世代にも公平に負担してもらうために行うものです。平成16年度は前年度より27億円増加したものの、旧楠町より33億円引き継いでおり、実質的な残高は減少しました。なお、市債の発行を計画的に行っており、今後は徐々に減少となる見込みです(グラフ(5))。 |
 |
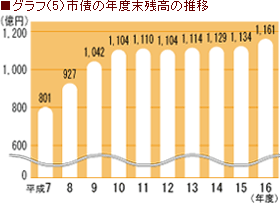 |
|
 |
|

