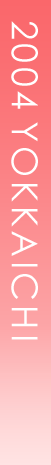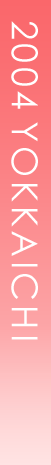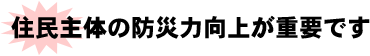 |
|
| 阪神・淡路大震災では、倒れた建物の下敷きになって生き埋めになった人や家具に閉じ込められた人のうち、救助された人の約95%は、自力で脱出したか、家族や隣人によって救出されています。消防などの専門の救助隊により救出されたのは、わずか1.7%でした(グラフ(1))。大規模災害発生時、特にその初期の段階では、消防などの公的機関が多数の被災者に対して迅速に対応することは困難であり、被災者同士で何とかしなければならない状況であったことが分かります。 |
|
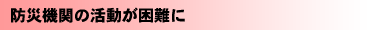 |
|
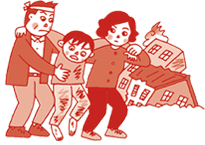 すなわち、災害が大きければ大きいほど、被災者数が増えるだけでなく、消防をはじめとする防災関係機関自身が被害を受けたり、道路や橋りょうなどの公共施設が被害を受けたりし、これらの機関の災害活動に支障を来たすケースが増大します。さらに、発災直後の初動期では、情報なども混乱し、防災機関による適切な対応が困難になることから、地域の皆さんが互いに助け合って人命救助や初期消火に努めることが、被害の軽減に大きな役割を果たすことになるのです。 すなわち、災害が大きければ大きいほど、被災者数が増えるだけでなく、消防をはじめとする防災関係機関自身が被害を受けたり、道路や橋りょうなどの公共施設が被害を受けたりし、これらの機関の災害活動に支障を来たすケースが増大します。さらに、発災直後の初動期では、情報なども混乱し、防災機関による適切な対応が困難になることから、地域の皆さんが互いに助け合って人命救助や初期消火に努めることが、被害の軽減に大きな役割を果たすことになるのです。 |
|
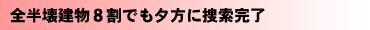 |
|
震源地に近い淡路島の北淡町豊島地区では、全半壊の建物が8割と甚大な被害状況であったにもかかわらず、近隣同士で救助活動が迅速に行われ、さらに地元消防団の活躍により、行方不明者の捜索が地震当日の夕方には終了しています。また、神戸市長田区真野地区では、日ごろからの緊密な連携に加え、自主防災組織の活動により、延焼防止、高齢者救出などが行われました。
|
|
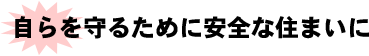 |
|
阪神・淡路大震災での死者の大半は、家屋の倒壊や家具の転倒によるものです。家具類の固定と住宅の耐震化など、自らの力で尊い命を守りましょう。
|
|
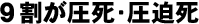 |
|
阪神・淡路大震災の犠牲者の九割近くは、愛するわが家の倒壊や家具などの転倒による圧死または圧迫死でした(グラフ(2))。地震からあなたと家族の大切な命を守るためには、家具類の固定はもちろん、住宅自体の耐震化が必要です。まずは耐震性を確認し、必要なら耐震改修をするなどの対策を講じましょう。また、比較的簡単にできる家具類の固定などは、すぐにでも行いましょう。
|
|
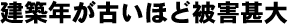 |
|
阪神・淡路大震災での建物の被害状況を建築年代ごとに比較すると、昭和56年の建築基準法改正(耐震基準の見直し)以前に建てられた建物の被害が多く、建築年が古いほど被害が大きくなっています(グラフ(3))。
|
|
 |
|
さらに、倒壊家屋は道路をふさぐなど、消火や救出救助活動、避難などの障害になり、地震被害をさらに大きなものにしてしまうのです。
|
|
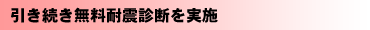 |
|
このようなことから、本市でも、建築基準法が改正された昭和56年6月1日以前に工事着工された一般木造住宅を対象に、無料で耐震診断を行う制度をスタートさせました。来年度も継続して実施していく予定ですので、ぜひ、ご活用ください。詳細については、改めて「広報よっかいち」などでお知らせしていきます。
|
|
 |
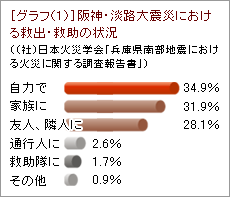 |
|
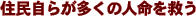 |
 |
「人と防災未来センター」語り部
谷川三郎さん
元 芦屋市建設部長(震災当時) |
 市職員の出勤状況は、自らの被災などもあって当日夜で42%。すぐに救出活動を始め、1日目は発見者82人中60人が生存。2日目は22人救助して5人が存命。3日目には19人救助したが、全員が死亡していた。市による救出活動以前に、多くの人が近隣住民により救出された。発災直後の迅速な救出活動で多くの人命が救える。1時間でも遅れたら多くの命がなくなる。自主防災組織の重要性を痛感した。 市職員の出勤状況は、自らの被災などもあって当日夜で42%。すぐに救出活動を始め、1日目は発見者82人中60人が生存。2日目は22人救助して5人が存命。3日目には19人救助したが、全員が死亡していた。市による救出活動以前に、多くの人が近隣住民により救出された。発災直後の迅速な救出活動で多くの人命が救える。1時間でも遅れたら多くの命がなくなる。自主防災組織の重要性を痛感した。 |
 |
| 市では、防災講演会の開催のほか、自治体や各種団体の要望に応じて出前講座などを行っています。ぜひ、ご聴講ください。 |
|
|
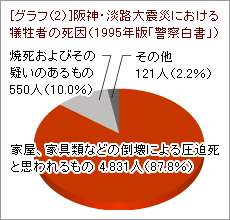 |
|
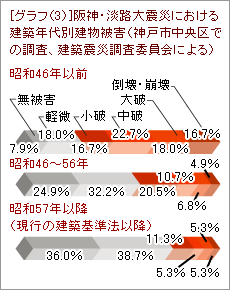 |
|