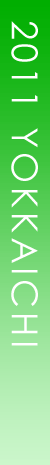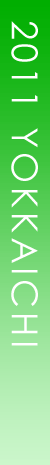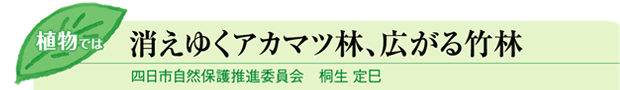 |
| |
 |
少年自然の家に
わずかに残るアカマツ林 |
人々がアカマツを薪や建築用材に利用していたころは、市の丘陵地から山林にかけて、多くのアカマツ林が見られました。毎年、冬になると葉が茶色く変化し弱ってきたアカマツは伐採し、薪に利用することで、松枯れの拡大を防ぎ、アカマツ林を守ってきました。
ところが、1960年ごろから化石燃料の普及とともに、薪が利用されなくなってくると、次第にアカマツ林に人の手が入らなくなり、放置された林は遷移が進み、ヒサカキ、カクレミノなどの常緑広葉樹が密生して薄暗くなりました。さらには、マツノザイセンチュウによる松枯れの被害もどんどん広がり、市内ではアカマツ林があまり見られなくなりました。
十分な日光が入る明るいアカマツ林だったからこそ生きていくことができた多くの植物が姿を消し、葉や実を食べていた昆虫や野鳥も姿を消していきました。
一方、市内に多くあった竹林は、生活の中で竹を利用することが少なくなってきたことで急激に増殖し、日光をさえぎり、他の樹木の生育を妨げるなど生態系に大きな影響をあたえるようになってきました。
このように、里山の林の姿は人の生活と深い関わりを持っています。 |
|
 |
|
 |
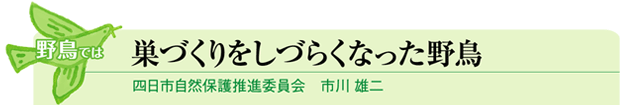 |
| |
 |
| シロチドリ |
約20年前の調査と比べると、鳥の種類によっては個体数の増減が確認できました。
まず、カワウやアオサギなどの大型の魚を主食とする鳥は増加しており、このことから、以前に比べて河川の水質が改善して魚が戻ってきていると考えられます。しかし、その一方で、主にフクロウなどの大木の洞穴で巣をつくる鳥が減少しています。県の鳥であるシロチドリも、巣づくりの場所である海岸の自然環境の変化や人の立ち入りなどによって減少しており、人間の活動は野鳥に大きな影響を与えています。 |
|
| |
|
 |
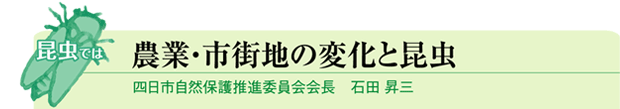 |
| |
 |
| マユタテアカネ |
50年ほど前までは、秋になると、チョウの一種であるイチモンジセセリの大群が伊勢湾からやってきて市街地を飛びぬけ、山の彼方(かなた)へと移動していったものです。こうした光景が1960年代後半からはほとんど見られなくなりました。これは、イネの品種改良により、大移動する世代が育たなくなったのが原因です。
また、1980年ごろまでの田んぼには、アキアカネ、ナツアカネ、マユタテアカネなどの赤トンボが満ちあふれていましたが、最近では丘陵に残る小さい田んぼでしか見られなくなりました。稲作の方法が変わり、短期間しか田んぼに水を入れなくなったため、幼虫の成長期に必要な水がなくなり、赤トンボは生きられなくなったのです。
また、セミに着目してみると、昔は市街地で普通に見られたニイニイゼミやアブラゼミがいなくなり、代わりにクマゼミが増えました。これは市街地の大部分が舗装され、雨水が染み込まなくなった地面が乾燥したためで、大型で生命力の強いクマゼミでなければ、市街地で生き抜くことが不可能になっています。 |
|
| |
|
 |
 |
 |
| 人の暮らしは自然界の生き物の営みに大きな影響を与えています。生活様式が変わるにつれ、周りの自然も変わっていきます。これからも自然環境を保全していくには、私たちが自然への理解を深め、自然に優しい暮らしを心掛けることが大切です。 |
 |
 |
| 環境学習センターでは、市民の皆さんと自然との触れ合いの機会が広がるよう、さまざまな自然体験や自然観察会を開催しています。家族などで気軽に参加しましょう。 |
 |
| ●問い合わせ/環境学習センター Tel 354-8430 |
 |

自然観察会 |
|
|
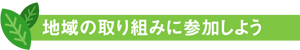 |
 |
三重西里山を愛する会
「しろやま倶楽部」 |
市内にはまちづくりの一環として里山整備などの自然環境の保全に取り組んでいる地域がいくつもあります。市でも「個性あるまちづくり支援事業」や「市民緑地制度」「市民に親しまれる公園ボランティア支援事業」などで、自然を大切にする取り組みを支援しています。 |
 |
| ●問い合わせ/「個性あるまちづくり支援事業」=市民生活課 Tel 354-8179、「市民緑地制度」=都市計画課 Tel 354-8214、「市民に親しまれる公園ボランティア支援事業」=市街地整備・公園課 Tel 354-8197 |
|
| |
|
|
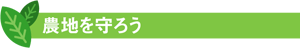 |
| 農地の維持は自然環境のバランスを保つ上で欠かせないものです。市では「優良農地保全事業」などにおいて農地の維持、継承を図っています。また、市民農園の開設促進を図り、現在、市内21カ所で市民の皆さんが利用しています。 |
 |
|
●問い合わせ/農水振興課 Tel 354-8180 |
|
|
|
|