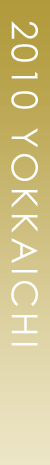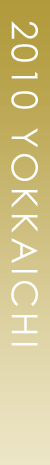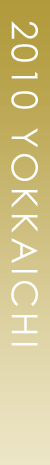 |
|
すばらしい日本の文化から学ぶ
(人権のひろば〜人権・同和教育シリーズ〜) |
 |
|
 皆さんは、この写真がどこか分かりますか。 皆さんは、この写真がどこか分かりますか。
これは、京都市の龍安寺(りょうあんじ)の石庭です。現在、小学6年生の社会科の教科書にも掲載されています。
この庭は、水や木が一切使われず、白砂の上に15の石を置いた「枯山水(かれさんすい)」と呼ばれています。庭の美しさに、つい目を奪われがちですが、石の裏には、この庭を造り出し、被差別の中を生き抜いてきた二人の「庭づくり」の名前が刻まれています。
教科書では、この庭が「そのころ差別されつつも、すぐれた技能をもった人々によってつくられたといわれています」と記述されています。
【深く理解するということ】
私たちの周りには、世界に誇れる文化がたくさん残っています。庭造(づく)りだけでなく、差別の中を生き抜いた人々が担い手となり完成させたものが、今もなお生き続けています。
能や猿回しといった芸能、竹や革(かわ)の工芸品など、これらの人々によって完成され、継承されてきたものが多くあります。
今後、皆さんがこのような素晴らしい日本の文化に触れる機会があれば、ぜひ思い出してください。差別の中を生き抜いた人々の果たしてきた役割を・・・。
歴史を深く理解することで、これまでとは違った日本の文化が見えてくるでしょう。 |
|
|
| ●問い合わせ先
…人権・同和教育課(Tel354−8253 Fax354−8308) |
|