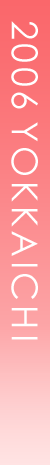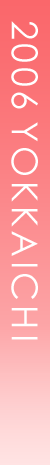|
|
 |
|
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、大きな被害を受けた建築物が多数みられ、地震などの災害から建築物の安全性を確保するには、工事中の検査体制を充実することが重要であると認識させられました。
建築物を建築する際の建築確認や検査は、従来、建築主事をおく県や市で行っていました。しかし、建築技術の発展、高齢化や省エネ化などの社会状況の変化、行財政改革が強く求められる中で、県や市だけではこれを実施することが難しい状況となってきました。
一方、民間では、住宅性能評価を保証する業務を実施するなど、多様なサービスの提供が可能となってきました。
このような状況で、平成10年に建築基準法が改正され、官民の役割分担の見直し、規制緩和という時代の要請に応じて、一定の要件を満たした国および都道府県が指定する民間機関で建築確認や検査を行うことができるようになりました。この指定を受けた民間機関が指定確認検査機関です。
建築主は、市と指定確認検査機関のどちらでも建築確認を受けることができます。指定確認検査機関は平成17年12月末現在、全国で124機関があり、市内では13機関が活動しています。指定確認検査機関での受け付け割合は、平成17年12月末現在、44.6%です。
指定確認検査機関では、確認済証を交付した場合、市に報告しなければなりません。市は、その建築計画が建築基準法などに適合しないと認めるときは、確認の取り消しをすることもできます。
構造計算書偽装問題を受けた建築基準法改正案では、建築確認、審査のあり方や行政の指定確認検査機関への関わり方などが見直される予定です。市としては、今後も建築基準法に基づき、安全な建築物を確保し、安全で安心なまちづくりにより一層取り組んでいきます。 |