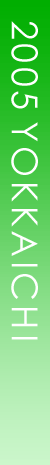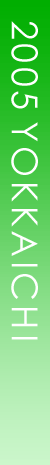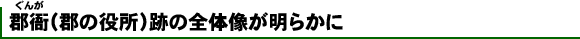 |
|
久留倍(くるべ)遺跡(大矢知町)は、弥生時代から室町時代にかけての遺跡で、東に伊勢湾を望む標高30メートルほどの小高い丘の上にあります。平成15年、この遺跡で古代(飛鳥、奈良時代)の郡衙(ぐんが)跡が見つかり、一躍脚光を浴びることとなりました。
この郡衙(ぐんが)跡は、主に政庁と正倉院から成り、政庁が先に造営され、後に正倉院が造られたと考えられています。政庁・正倉院が一体で発掘されたのは全国的にもほとんど例がありません。さらに、この遺跡は、壬申(じんしん)の乱(672年)や聖武天皇東国行幸(ぎょうこう)(740年)の舞台となった「朝明郡衙(あさけぐんが)」と考えられ、考古学のみならず古代史や万葉集の研究にも一石を投じる重要な発見となりました。 |
|
 |
|
| この場所は北勢バイパスの建設予定地のため、遺跡の保存について国・県・市が対応を協議し、政庁・正倉院を中心とした範囲を保存することになりました。今後は、国史跡指定を目指すとともに、市民の皆さんの憩いの場・学習の場となるよう整備を行っていく予定です。 |
|
| 【郡衙(ぐんが)】 |
郡は古代日本の行政区画(国(くに)、郡(ぐん)、郷(ごう))の一つで、郡衙(ぐんが)はその中心として地方行政の拠点となった施設(郡の役所) |
|
|
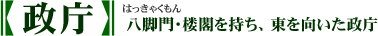 |
|
| 丘陵上部に伊勢湾を望む東向きに造営されています。東向きの政庁はほかに例がなく(通常は南向き)、朝明郡衙(あさけぐんが)の大きな特徴です。正殿、脇殿、八脚門(はっきゃくもん)などが「ロ」の字型に配置され、塀でつながっていたようです。規模は東西42メートル、南北51メートルで、前面に楼閣、背後に倉を備えています。楼閣を備えた郡衙(ぐんが)もほかに例がありません。 |
|
| 【八脚門(はっきゃくもん)】 |
名称は外見上八本柱の構造に見えることに由来している。実際には12本の柱が用いられている |
| 【政庁】 |
郡衙(ぐんが)の中心的な施設で、政務のほか儀式や宴会などが行われていた |
|
|
 |
|
| 丘陵東斜面に位置しています。東西約66メートル、南北約99メートルの区画溝が方形に巡り、その中に正倉群が並んでいた様子がうかがえます。区画溝はほかの官舎からの類焼を防いだり、正倉院への出入りを規制するものと考えられ、東側に出入り口が設けられていたようです。柱の直径は30から40センチメートルで、4本×4本か5本×4本の柱で造られていました。 |
|
| 【正倉・正倉院】 |
正倉は租税として徴収した稲もみなどを収納する国有の倉。多くの正倉群が「院」と呼ばれる一郭を形成し、これを「正倉院」と呼ぶ。正倉院といえば奈良東大寺の宝物庫が知られるが、本来は正倉群の一郭を指す |
|