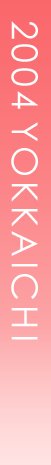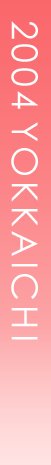|
|
| 少人数授業とは、授業をするときに学級をいくつかのグループに分け、少人数の学習集団単位で授業を行うものです。そのねらいは、一人ひとりの子どもの特性や違いに応じてきめ細かな学習指導を行い、確かな学力をはぐくむことです。また、「ティームティーチング」といって、クラスを分けずに複数の教員を配置し、教員がチームを組んで指導することで、子ども一人ひとりにきめ細かな対応ができる授業形態を取っている場合もあります。 |
|
 |
|
| 市では、少人数授業のため、国や県の補助や市の独自事業として教員の増加を図り、現在、68人の非常勤講師を配置しています。少人数授業を実施する学年や科目は、各学校の実情や子どもの実態に応じて違います。小学校の教科では「算数」が多く、次いで「国語」などで行われています。中学校の科目では「数学」、「英語」で多く取り入れられています。 |
|
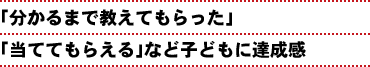 |
|
| 少人数授業では、教員が子どもたち個々に向かい合う時間が多く取れるため、子ども一人ひとりの「つまずき」、「伸び」、「変化」、「到達度」、「習熟度」などの状態が把握できます。それに応じて「つまずき」などへの対策や一人ひとりに適した教材を作るなど、個の特性にあった指導を進めることができます。子どもたちも分かるまで教えてもらうことなどで、「充実感」や「達成感」、「存在感」などを感じるようになります。 |
|
 |
|
| 少人数授業の成果は着実に現れています。その成果をさらに高めていくために、さまざまな課題への対応も必要です。今後は「発表する機会が増えたことで、次はその内容を充実させる」、「一人ひとりに自分の考えを持たせる」、「自分のペースで学べるよさだけでなく、みんなで学び合う時間を設ける」、「少人数だからできる、より効果的な指導法を見つける」などさまざまな課題への取り組みを進めます。教師間の打ち合わせ時間の確保や進度のズレを調整する工夫も必要です。少人数授業が子どもたちにとって「学校が楽しくなる」、「勉強が面白くなる」ための大きな力となるよう、さらにその充実に努めます。 |
|
 |
【子どもの声】
●先生の声が聞こえて分かりやすい
●みんな当ててもらえるし、黒板にも書ける
●手を挙げると当ててもらえるからやる気が出る
●分からないとき、先生に教えてもらいやすい
●分かるまで教えてもらえてうれしい |
【保護者の声】
●分からない子もきちんと教えてもらえる
●ノートへの計算の書き方など、
学習方法がきちんと身につく |
【教師の声】
●つまずいている子の把握がしやすく、
個々に応じた指導がしやすい
●到達度の違いを把握しやすい
●ノート、宿題など個々に丁寧な指導ができる
●一人ひとりをよく見て個人に掛ける時間を多くできる |
|
|
 |
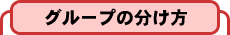 |
|
| 個々の子どもの特性や希望を考慮して分けます。いくつかの方法がありますが、主に3つの方法が用いられています。 |
 |
●学習内容の習熟度に応じて
例:算数などで確実に理解を深めていくとき |
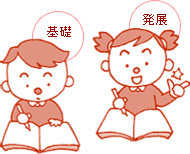 |
 |
●学習する課題や興味に応じて
例:社会科などで分野を分けて調べるとき |
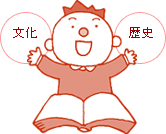 |
 |
●均等に人数を分ける
例:同じ内容を学習するときや習熟度の違う子ども同士が互いに助け合って学習するとき |
|
 |
|
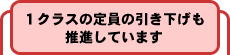 |
|
| 三重県では、1学級の編成基準を30人に引き下げて、1クラスの人数が25〜30人となるよう、学級そのものを少人数にする取り組みを進めています。これにより児童と担任とのかかわりを増やし、よりきめ細やかな教育を行っています。現在、小学校1年生を対象に実施されていますが、来年度は2年生にも拡大されます。 |
|
| (1年生76人の場合)少人数学級の例 |
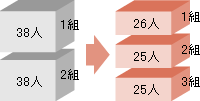 |
| ※これまで38人ずつの2クラスであったものが、26人、25人、25人の3クラスになります |
|
 |
|
|