 |
|
現在、パソコンは職場だけでなく家庭にも広く普及しています。国内のパソコン出荷台数は過去3年間で3,000万台を超え、その約4割が家庭用といわれます。
また、家庭から廃棄される使用済みパソコンは、平成15年度は約1万2,000トン、平成25年には6万トンを超えるとされます〈(社)電子情報技術産業協会の試算〉。
これまでは家庭の使用済みパソコンは埋立ごみとして処理されていましたが、きちんとリサイクル処理すると、鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、金、銀、コバルトなどが資源として再利用できます。「資源有効利用促進法」に基づく「PCリサイクル」は、消費者とメーカーが協力しながら、使用済みパソコンを再資源化し、廃棄物削減と資源の有効利用を目指すものです。 |
|
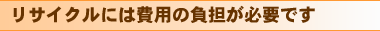 |
|
「資源有効利用促進法」では、9月30日以前に買ったパソコンは処理する時に回収・リサイクル料金が必要です。10月1日以降に買うパソコンには判別マークとして「PCリサイクルマーク」がついています(図(1))。このマークの付いたものは販売時に回収・リサイクル費用が含まれており、処理時にメーカーが無償で引き取ります。
リサイクルの対象となるのは、パソコン本体(ディスプレイ一体型を含む)、ディスプレイ(ブラウン管式、液晶式)、キーボードやマウスなどの付属品(注(1))です。プリンターやスキャナーなどの周辺機器、ワープロ専用機などは対象外です。 |
|
| (注(1))付属品とは、メーカーなどが販売時にパソコンと一体で同梱したキーボード、マウス、スピーカー、ケーブル類などです。 |
|
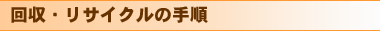 |
|

