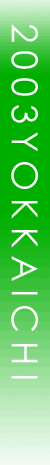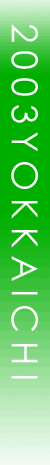|
|
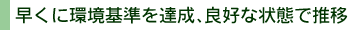 |
|
| 昭和30年代から40年代の市の大気汚染の主な原因は、工場から排出される硫黄酸化物でした。39年に本市は「ばい煙の規制等に関する法律」の指定地域になり、43年には「大気汚染防止法」による排出規制が行われ、硫黄酸化物の環境濃度については、かなり改善されました。47年には「三重県公害防止条例」(現「三重県生活環境の保全に関する条例」)により総量規制が実施され、翌48年からは排煙テレメーターシステムにより、工場の排煙状況を常時監視するようになりました。その結果、51年度には、全国11の総量規制指定地域の中でいち早く環境基準を達成し、以降は良好な状態で推移しています(グラフ(1))。 |
|
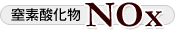 |
|
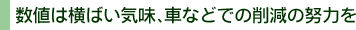 |
|
窒素酸化物は、主に物の燃焼で発生し、発生源は工場や自動車などです。工場などには「大気汚染防止法」や「三重県公害防止条例」により規制などが行われました。自動車には排出ガス規制が進み、平成13年12月に本市は対策地域に指定され、平成14年10月には、トラック、バス、ディーゼル乗用車などの車種規制が開始されました。
また、市では昭和48年から自動測定による窒素酸化物の常時監視を開始し、その後、順次測定局を増やし、監視体制の充実を図っています。それによると、二酸化窒素濃度は下降気味または横ばいの数値を示しています(グラフ(2))。 |
|
 |
|
| 市の大気汚染の常時監視は、昭和37年に磯津町で二酸化硫黄の測定を開始して以来、測定網を拡大してきました。現在、一般環境大気測定局九局、自動車排出ガス測定局二局で監視しています(図(1))。測定データは、コンピューターを利用したテレメーターシステムで市役所に収集され、大気汚染の状況の監視と市民への情報提供などに使われています。また、広域的に大気汚染の状況を把握するための簡易測定法による二酸化窒素の測定を28地点で実施しています。 |
|
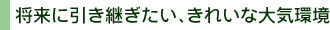 |
|
| 良好な環境の保全と創造は、すべての人の積極的な取り組みと参加によって行われることが必要です。市は、大気環境の保全を目指し、平成7年3月に「四日市市環境基本条例」を制定して四日市市環境計画を策定し、同年9月には「快適環境都市宣言」を行いました。市民、事業者、行政が一体となって、みんなで大気環境の保全に努め、良好な環境を将来に引き継いでいきましょう。 |