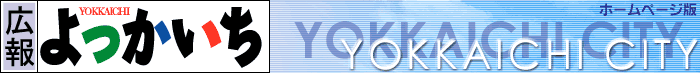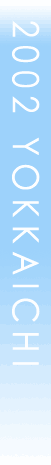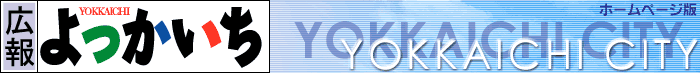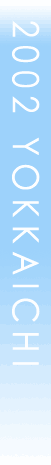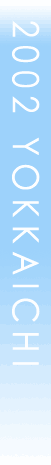 |
|
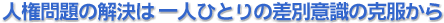 |
|
昨年、11月上旬号の「同和教育シリーズ」(人権はどうして大切なのだろう?)では、人権問題についての研修会に参加した「私」の「声」を引用しました。それは、自分の中にある差別心になかなか気付くことができず、迷いながらも少しずつ自分なりに考えてみようとする内容でした。

その「声」に対して市民の方からご意見をお寄せいただきましたので、その内容の一部をご紹介します。
懇談会で、ちょっと言うと、かなり突っ込まれるということを耳にします。ちょっと言った言葉に差別的な内容が含まれていることに気付かないため、指摘されると「突っ込まれた」ということになってしまうようです。

また、その言い方や内容が「厳しい」といわれますが、私は思うことがあります。私自身も、自分の障害をからかわれたとき、思わず言葉を荒らげて言い返したことがあります。人は、自分のこととなると真剣にならざるを得ないのです。

差別について考えるとき傍観者的なところに自分を置くことをやめて、差別をなくすために自分に何ができるか考え、行動してみませんか。世の中から人権侵害がなくなれば、人とのつながりが切れることも、虚しさがこみ上げてくることもきっとなくなります。互いにがんばりましょう。
(以上引用) |
つまり、一人ひとりが、自分の心の本音の部分と向き合い、差別がなくなっていないことを自分自身の課題としてとらえることが大切なのです。そして、自らの差別意識を克服していくことが、同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決につながるのではないでしょうか。
(今回は、教育委員会 人権・同和教育課が担当しました。) |
|
|
|
|
|